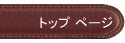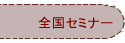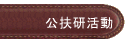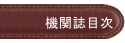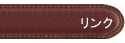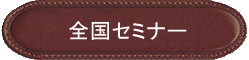
申込書は最後に有ります。
| 公的扶助・社会福祉の制度『改正』と利用者の権利保障を考える | |||
| ―構造改革で“人間の尊厳”はどうなるか― | |||
| と き;2001年11月15日(木)~17日(土) | |||
| ところ;熱海後楽園ホテル(静岡県熱海市) |
心から全国の福祉職場で働くみなさんのご参加をよびかけます!
| 厚生労働省では現在、生活保護制度の見直し作業がはじまっています。この間の厚生労働省関係者の発言によれば、今後の見直しの論点として、①生活保護基準は全体としては高すぎるのではないか、②雇用につなぐための方策や経済的な自立にむけたインセンティブが不十分ではないか、③保護実施の手続きや要件の簡略化が必要ではないか、などが想定されていると思われます。最近の厚生労働省の方針は、ホームレスへの生活保護適用に見られるように、「適正化」一辺倒の保護行政に変化のきざしも感じられます。これを受けて各地の福祉事務所でも“水際作戦”とよばれる相談窓口での厳しい受給制限が徐々に変化してきています。その反面、最低生活基準を相対化し、なし崩しに最低生活の水準低下を図っているふしもうかがわれます。このような状況をふまえて、私たちは今回のセミナーの重要な柱の一つとして、生活保護制度「改革」の問題をとりあげます。改めて生存権保障の視点から、公的扶助を中心とする社会福祉制度のあり方を考えてみたいと思います。 |
| 介護保険施行後1年が経過しました。この間、制度自体の様々な問題点が明らかになってきました。また、今年10月からは保険料の満額徴収とともに滞納者への給付制限も始まろうとしています。介護保険や高齢者保健福祉に関しては各自治体ごとに、施策事業の質量に相当の格差が見られる状況です。私たちは、このセミナーを通じて先進自治体の経験を共有し、区市町村という基礎的自治体や福祉事務所が直接高齢者・家族への相談援助を行うことの意義を再確認したいと考えています。 |
| 2003年4月から、障害者福祉の分野に支援費制度が導入されようとしていまが、ようやく去る8月23日に厚生労働省から「事務の大要」など一定の考え方が示されました。介護保険制度では、給付限度額設定や費用負担によって実質的な利用制限が生じる等の問題が起きています。この制度の具体化にあたっては、こうした問題を生じないようにすべきです。また、障害者への相談援助に区市町村や福祉事務所がどのように公的責任を負うのかが問われていくと思います。 |
| 全国の福祉職場で働くみなさん!天下の名湯、熱海の湯に浸りながら、大いに日本の福祉のあり方を語り合い、21世紀を人権と福祉の世紀にする展望をつかもうではありませんか。 |
| 心からあなたのご参加をお待ちしています。 |
《主 催》 全国公的扶助研究会・第34回公的扶助研究全国セミナー実行委員会
《後 援》
静岡県・熱海市・静岡県社会福祉協議会・熱海市社会福祉協議会・静岡県社会福祉士会・静岡県精神保健福祉士協会・静岡県手をつなぐ育成会・静岡県精神障害者家族会
熱海市観光協会・静岡新聞・SBS静岡放送・テレビ静岡(順不同)
《タイムテーブル》
*11月15日(木):全体会
|
12:00 13:00 17:15 18:30 |
||||||
| 受付 | 開会全体会 | 懇親会 | ||||
| 基調報告・記念講演・他 | ||||||
*11月16日(金):学校・講座・分科会
| 9:30 2:00 13:00 17:00 8:30 | ||||||
| 学校・講座 | 昼食 | 学校・講座 | 夕 食 | |||
| 分科会 | 休憩 | 分科会 | ||||
*11月17日(土):自由選択講座
| 9:00 12:00 | |||
| テーマ別自由選択講座 | 散 会 | ||
《1日目》全体会
*基調報告
第34回公的扶助研究全国セミナー実行委員会
*記念講演「ハンセン病訴訟の経過とその勝訴が意味するもの」
平沢保治 氏(多摩全生園入園者自治会会長)
*映画「人間裁判―朝日訴訟」上映
*基調講演「人間らしく生きる権利とは何か―朝日訴訟を現代に生かす」
朝日健二 氏(医療福祉総合研究所主任研究員)
《2日目》学校・講座
*生活保護ケースワーカーのための初級学校
毎回のセミナーで大好評の初級学校を今年も開校します。ケースワーカーになったばかりというあなた。まだ経験2~3年で仕事に行き詰まりを感じている中堅ワーカーのあなた。ぜひ参加してみてください。きっと日頃の悩みや疑問の解決に役立つことと思います。
(第二講で使いますので、実施要領を持参してください。)
第一講「公的扶助の歴史・理念と生活保護法の今日的な役割」
尾藤廣喜 氏(鴨川法律事務所)
第二講「生活保護法・実施要領の活用法(入門編)」
森 宣秋 氏(元・京都市保健福祉局地域福祉課)
第三講「ケースワーカーの悩み,喜び,働きがいについて」
沼田崇子 氏(岩手県盛岡地方振興局保健福祉環境部)
=バズ・セッション(小グループに別れての自由なおしゃべりの時間)=
補講・まとめ「生活保護の仕事にロマンを求めて」
藤城恒昭 氏(城西国際大学)
*査察指導員のためのリフレッシュ講座
査察指導員の仕事は、大変な気苦労を伴うものです。ケースワーカーに対する相談・アドバイスを求められ、ときにはクライエントの解決困難な相談への直接対応も迫られる…。また、業務の進行管理・職員管理の役割も担い、とかく上から下からの“板挟み”になりがちです。この講座では、よりよい査察指導とは何か? この悩み多い仕事を燃え尽きず続けていく秘訣は?…etc. 新人および先輩指導員の経験談を素材にして語り合います。
第一講「査察指導って何?-ケースワーカーと共に成長する査察指導員をめざして」
平野 治 氏 (東京都三鷹市福祉事務所)
第二講「査察指導あれこれ・ABC」
横山立夫 氏 (名古屋福祉法経専門学校・元三重県南勢志摩保健福祉部)
=グループディスカッション(気軽に悩みを出し合う時間)=
補講・まとめ
長友祐三 氏 (東京都目黒区福祉事務所)
*政策研究講座「生存権保障の視点から生活保護制度の<改革>を考える」
今、生活保護の現場は、ケース数の増加、地区担当員の経験年数の短期化等、厳しい状況にあります。同時に、地方分権の中で、介護扶助の新設とそれに伴うケアマネジャーとの連携その他、生活保護の実施体制が様々に変化しています。そうした中で、今最も大切なことは、生存権保障の原点に戻って、生活保護のあるべき姿を構築することではないでしょうか。新人の方もベテランの方も、また、生活保護以外の分野の方もぜひ一緒に考えてみませんか。
第一講「憲法第25条と生活保護法―生存権の意義を考える」
笹沼弘志 氏(静岡大学)
第二講「公的扶助をめぐる国際的動向―イギリスを中心に」
木戸利秋 氏(日本福祉大学)
第三講「生活保護の実施体制と運用をめぐる諸問題について」
金杉典子 氏(東京都福祉局)
《2日目》分科会
*第1分科会「生活保護のケース処遇とケースワーカーの相談援助を考える」
生活保護制度の見直しの動きにかかわって、現行制度の「自立助長」をどのように評価すべきか、さらには公的扶助における経済給付と相談援助とを一体としていくべきか、分離すべきかが重要な論点としてクローズアップされつつあります。現場からの実践報告、研究者からの問題提起をふまえ、現代的貧困をどのようにとらえるのか、どのような相談援助が求められているのかを考え、ケースワーカーの仕事の二面性とその克服の展望を探ります。
*第2分科会「争訟事例をふまえて生活保護制度の運用を再点検する」
生活保護制度は、法律や実施要領にもとづいて運用されることになっています。しかし、果たして本当にそう言い切れるでしょうか。全国各地で多発している不服審査請求事件の内容を見ると、多くの場合、その背景に法律にも実施要領にも根拠のない“行政慣行”がある場合が少なくありません。最近の審査請求の具体的事例を素材にしながら、同様の誤った制度運用が私たちの職場の中にないかを再点検してみようではありませんか。
*第3分科会「野宿からの脱出のために私たちは何ができるのか?」
野宿を余儀なくされている人は、毎年増え続け、大都市だけでなく地方都市にまで広まり、全国で2万人以上といわれています。こういった中、大都市では自立支援センターが開設されつつありますが、はたしてこれで問題が解決するのでしょうか。各地でとりくまれてきた実態調査についての報告、自立支援センターからの報告、福祉事務所の現場での実践報告を受け、今、野宿からの脱出に何が必要なのか、生活保護の果たすべき役割は何かを考えます。
*第4分科会「子どもたちは今―福祉事務所には何ができ、何をすべきか」
家族・親子の中で、子どもたちは今、どういう状況に置かれているのでしょうか。生活保護を受けている家族には、生活の安定や一人ひとりの成長を図る上で多面的な援助が求められます。しかし、地区担当員は、ケースワーカーとは呼ばれても、経済的給付に付随する事務に追われ、なかなか本当に必要な援助ができない現状にあります。多問題を抱える世帯、とりわけ次代を担う子どもたちの生活のためにはどのような援助が必要か、関係機関と一緒に考えたいと思います。
*第5分科会「高齢者の生活保障と介護保険・高齢者保健福祉の課題」
介護保険が始まって1年半、ケアマネジャー、ホームヘルパー等に期待される本来の福祉・介護労働は大きく歪められ、限定的なサービスの切り売りという状況が生み出されています。また、区市町村や福祉事務所も高齢者に対し十分な相談援助ができない状況にあるようです。しかし、高齢者の生活をトータルに支援する先進的な取組みも生まれています。高齢者にとって本当に求められる相談援助実現のために、私たちに何ができるのかを考えてみたいと思います。
*第6分科会「支援費制度の下での障害者福祉と相談援助のあり方を考える」
支援費制度には介護保険と同様に“市町村の相談援助機能がなくなる”、“内容次第では、サービス水準の低下や負担増が生じる”等の不安の声が高まっています。ようやく厚生労働省から、大枠が提示されました。その内容は不確定な部分が多く、いくつかの問題点もありますが、市町村の役割も明示されています。厚生労働省他各方面からのシンポジストと共に具体化に向けた相談援助のあり方とシステムづくり、区市町村・福祉事務所が果たすべき役割について考えます。
*第7分科会「生保ワーカーのみなさん!聞いてください精神障害の方の声を!」―整いはじめた精神障害者福祉をさらに発展させるために―
精神障害者福祉がようやく整いはじめ、精神障害者も地域生活が容易になってきました。しかし,大阪の児童殺傷事件を契機に再び誤解と偏見が強まり,流れが後戻りする危惧があります。また、精神障害者に戸惑うケースワーカーが増え、病気への無理解から多くの当事者が不利益を受けています。精神医療サバイバー(精神障害を抱える当事者)が、生活保護生活の“暮らしにくさ”を語ります。また、児童殺傷事件の影響等について、ジャーナリスト、社会復帰施設職員から報告を受け、今後における精神障害者福祉と生活保護のあり方を考えたいと思います。
*第8分科会「アディクションと向き合う-癒し系との出会い」
-他人を変えようともがくより、自分を変える勇気を!-
アルコール・薬物依存症、摂食障害、DV(家庭内暴力)、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、AC(機能不全家庭で育ちトラウマを持つ人)等、稼動年齢層でも働けない、明確な病気はないが生きづらさを抱えている。そんなクライアントの処遇に悩んでいませんか。一人では関わりきれず疲れてしまいます。クライアント自身に回復を学ぶのはどうでしょうか。自助グループや精神神経科のグループワークでライアントは生き生きと甦ります。悩めるケースワーカーのみなさん!“回復”という名の汽車に乗ってみようではありませんか。
*第9分科会「女性の人権と福祉を支える―関係機関の役割と福祉事務所」
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)が施行され、来年4月には「配偶者暴力支援センター」が開設されます。一方、いくつかの自治体では一時保護や相談事業を民間委託するという動きがあります。生活保護相談の中でも、夫の暴力や子供への虐待が離別の原因となった事例が少なくありません。母子・女性相談員等とともに緊急対応を迫られる場合も多くなっています。関係機関とのダイナミックな連携が、女性の自立支援への決め手です。様々な動きや取組み報告を受け、女性の人権・福祉・自立をめざす援助活動について考えます。
《3日目》テーマ別自由選択講座
初めての試みとして6つの講座を設けました。2日目の学校・講座分科会の単なる延長ではありませんが、より議論を深めるきっかけになることを期待しています。自由に講座を選択して参加してください。
*テーマ(Ⅰ)「『構造改革』と21世紀の社会保障・社会福祉を考える」
第1講「社会福祉『改革』の流れを読む―介護保険と支援費支給制度を中心に」
平野方紹 氏(厚生労働省社会援護局総務課)
第2講「介護保険導入から医療制度『改革』への流れを読む」
朝日健二 氏(医療福祉総合研究所主任研究員)
*テーマ(Ⅱ)「生活保護裁判が問いかけるもの」
第1講「生活保護裁判の動向と争点について」
竹下義樹 氏(弁護士・生活保護裁判連絡会)
第2講「ケースワーカーと生活保護裁判」
下村幸仁 氏(広島市南福祉事務所)
*テーマ(Ⅲ)「生活保護制度改革をめぐる論点と課題」
第1講「生活保護法改正試案について」
林 直久 氏(生活保護裁判連絡会事務局)
※講義に先立ち2日目の政策研究講座及び第1・第2分科会の論議の概要報告を営スタッフか行い、その内容を受けて、新しい生活保護制度への展望を講師が示していきます。
*テーマ(Ⅳ)「ホームレス対策の現状と解決の展望を探る」
第1講「路上に生きる人々はいま」
宮下忠子 氏(ノンフィクションライター)
第2講「路上生活者の生活実態と地方自治体の果たすべき役割」
原 昌平 氏(読売新聞大阪本社科学部)
*テーマ(Ⅴ)「契約利用制度と利用者の権利・自治体行政の役割を考える」
第1講「介護保険制度のもとでの市町村・福祉事務所の役割を問う」
小川栄二 氏(立命館大学)
第2講「支援費支給制度と障害者の権利保障・権利擁護を考える」
塩見洋介 氏(大阪障害者センター)
*テーマ(Ⅵ)「児童虐待,DVの実態と対策の現状、これからの課題」
第1講「児童虐待問題をめぐる現状とこれからの課題」
野村一枝 氏(子どもの虐待防止センター)
第2講「女性の人権・福祉とDVをめぐる現状とこれからの課題」
若尾典子 氏(広島女子大学)
参加申込・問い合わせについて
《参加方式》
*会場兼宿泊場所:熱海後楽園ホテル
◎住所 〒413-8626 熱海市和田浜南町10-1
◎電話 0557-82-0121
◎交通 JR東日本 熱海駅(東海道新幹線・東海道線)下車
◎送迎 熱海駅からホテルバスで随時送迎します。
なお、受付開始時間帯は混雑が予想されます。余裕を持ってお出かけください。
*宿泊方式:原則として期間中は会場である熱海後楽園ホテルに宿泊となります。
グループ別(男女別)相部屋。但しグループ人数が定員以下の場合、他のグループと一緒になることもあります。
《参加費・宿泊費等》
*参加費:一般 10,000円,公扶研会員 8,000円,学生 5,000円(資料代;各 3,000円を含む)
*宿泊費:全日程参加(二泊五食付)34,000円(初日宿泊18,000円、2日目宿泊15,000円)
*2日目昼食:1,000円(日帰り又は1泊者)
《受付期間・申込書送付先》
*受付期間:原則として10月31日までに申込みしてください。
*申込書送付先:旅ジェットトラベルセンター
◎住所 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-9-7 グローリア初穂309
◎FAX 045-316-4356
*費用支払い:旅ジェットトラベルセンターから振り込み用紙を送付します。(確認後1週間以内に振り込みください。なお、手数料は申込者負担です。)
《問い合わせ先》
*全国セミナーについて:公的扶助研究会事務局
◎住所 〒345-8511 富士見市鶴馬1800-1 富士見市福祉事務所内
◎電話 0492-51-2711 榎戸(高齢福祉課) 岸田(福祉課)
◎FAX 0429-51-1025(宛先銘記のこと)
*費用・宿泊・会場等について:旅ジェットトラベルセンター
◎住所・FAX:上記の通り
◎電話: 045-312-2254 熊沢
*E-mailでの問い合わせ:kofuken@npo-jp.net

Copyright(c) 2000 All Jpan Reseach of Public Assistance . All rights reserved
itoisan@excite.co.jp